一眼レフカメラを手にしたばかりの頃、私たちは“何をどう撮ればいいのか”という漠然とした迷いに包まれます。設定は?構図は?そもそもこのカメラで、何を撮りたかったんだろう…。
そんな一歩目の戸惑いに、今日はそっと光を当てたいと思います。
大丈夫。写真は「好き」から始めても、ちゃんと育っていきます。
1. まずは“オート”でも構わない|気軽にシャッターを切ることから始めよう
カメラを買ったとたんに、F値・ISO・シャッタースピード…と専門用語に囲まれて息が詰まりそうになった経験、ありませんか?
でも、まず覚えていてほしいのは、「オートモードでいい」ということ。
写真の本質は“設定を完璧にすること”ではなく、“何を見つめて、どう残したいか”という心の向きです。最初からすべてを理解しようとしなくていい。
大切なのは、カメラと一緒に“まなざしを育てていく”ことです。
オートモードは「逃げ」じゃない。感性を育てる第一歩
「オートは初心者向けで、早く卒業すべき」——そんな言葉に焦る気持ちはよくわかります。でも、オートモードは“判断を機械に預けることで、自分の感じた瞬間に集中できる”というメリットがあります。
たとえば、道端に咲いた花が夕日に照らされていたとします。そのとき、“設定をどうしよう”と迷っているうちに、光はもうそこにはないかもしれません。
オートモードは、「感じたときにすぐ残せる自由」でもあるのです。
シャッターを押す「習慣」を、まずは10日間続けてみる
大きなことをしようとしなくてもいい。まずは、“1日1枚、何かを撮る”という小さな習慣をつくってみてください。
それは愛犬の寝顔かもしれないし、コーヒーの湯気かもしれないし、ただの空かもしれない。
でも、毎日シャッターを押しているうちに、自分の中の“好き”や“気になる”が少しずつ輪郭を持ってきます。
そして、気づけばそれは、あなただけの視点になっていくのです。
2. 構図を“考える”前に、“感じる”を大切にする
「構図を意識して撮りましょう」と言われると、どこかで“正しい形”に当てはめなきゃというプレッシャーが生まれがちです。
けれど、構図とは本来、“どこを切り取ったら気持ちいいか”を探す作業。
知識として学ぶよりも先に、まずは心が動いた瞬間を、自由にファインダーで追いかけてみてください。
この章では、構図を感覚でつかみ、写真に“自分らしさ”を添えるためのヒントをお届けします。
「三分割法」は正解じゃなく、きっかけにすぎない
写真の教則本によく出てくる「三分割法」。たしかにバランスの取れた構図をつくりやすい技法ではありますが、それに縛られる必要はまったくありません。
むしろ大切なのは、「どこに被写体を置くと、気持ちがすっと落ち着くか」。
たとえば、少しだけ左に寄せてみる。被写体の視線の先に余白を作ってみる。
そうした微調整を繰り返す中で、“自分だけの配置感覚”が少しずつ育っていきます。
気になったらまず立ち止まる。それが構図感覚のはじまり
上手な構図をつくるには、技法よりも「立ち止まること」の方が大事かもしれません。
たとえば、何気なく歩いている途中で、影が綺麗だなと思ったとき。
その感覚を大切にして、立ち止まり、視点を変え、しゃがんだり見上げたりしてみてください。
すると、今まで見えていなかった“切り取りたい瞬間”が、少しずつ浮かび上がってくるはずです。
構図感覚は、“いい景色”を探すよりも、“気づく力”を育てることから始まります。
3. 光を読む目を育てる|写真は“光の記録”である
一眼レフカメラを使う最大の喜びのひとつが、“光を写しとる”という感覚に触れられること。
写真とは、光のかたちを記録する行為でもあります。
この章では、朝・昼・夕、それぞれの光の魅力や、逆光や斜光といった「心を動かす光」の捉え方を紹介します。
数字より先に、“感じる”ことを覚えていきましょう。
逆光の美しさに気づけたら、写真は一気に変わる
逆光は“撮りづらい光”と思われがちですが、実はとても詩的な光です。
人物の輪郭がふわりと浮かび上がったり、葉の透明感が際立ったり。
その柔らかい輝きは、被写体に“物語”をまとわせてくれます。
露出が難しいと感じる場合は、まずシルエットとして捉えてみるのもおすすめです。
黒くつぶれてもいい。ただ、その場に流れていた“空気ごと”写真に写せたら、あなたの写真はぐんと深くなるはずです。
“順光”より“斜めの光”を探してみる理由
日中、太陽が真上にあると光が平坦になりがちですが、朝夕の斜光には陰影が生まれます。
影があることで、写真に“奥行き”と“温度”が加わります。
たとえば、窓から差し込む光が壁に模様を描いていたら、ぜひシャッターを。
その“斜めの光”があるだけで、何気ない風景がドラマに変わる瞬間があるのです。
光を読む力は、経験とともに育っていきます。まずは、「どんな光に心が動いたか」を覚えておくことから始めてみてください。
4. F値やISOより大事なこと|設定より“伝えたい気持ち”を優先する
カメラを使いこなしたい、もっと上手くなりたい——そんな気持ちが芽生えると、F値・ISO・シャッタースピードなど、設定への関心が高まります。
でも、いちばん大事なのは“その写真で何を伝えたいか”という、気持ちの部分です。
この章では、最低限覚えておきたい設定の意味と、設定よりも大切にしてほしい「表現したいこと」の見つけ方をお話しします。
F値より“どんな印象を残したいか”を考えてみる
背景をぼかしたいからF1.8。全体にピントを合わせたいからF8。
それももちろん正解ですが、まずは“どんな印象を写真に残したいか”を考えてみてください。
たとえば、大切な人のやさしい表情を撮るとき。背景は思いきりぼかして、その人の存在感だけを際立たせたいなら、開放F値を選びます。
反対に、広がる田園風景をすべて記録に残したいなら、F8〜F11でしっかり全体にピントを合わせてみましょう。
F値は数字ではなく、「想いを形にするためのツマミ」だと考えると、ぐっと写真が感情に寄り添ってくれます。
ISOは“明るさ”じゃなく“雰囲気”を決める道具
ISOは“暗いところで明るく撮る”ための機能——そう教わることが多いですが、実は「写真の空気感」をコントロールするツールでもあります。
たとえば、夜の喫茶店で撮る1枚。ISOを上げて明るくすることもできるけれど、あえて暗めに残して、“静けさ”や“孤独感”を表現してもいい。
ISOの数値が変わると、ノイズの乗り方や質感も変わります。
“明るければ正解”ではなく、“伝えたい雰囲気”をイメージして調整してみてください。
5. 撮ったあとの「振り返り」が、あなたの写真を育てる
撮った写真をそのまま放置していませんか?
シャッターを切ることが「見る訓練」なら、見返すことは「感じた自分を知る訓練」です。
この章では、“撮影のあとにできること”を紹介します。
写真は撮って終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートかもしれません。
お気に入りの3枚だけ選ぶ、という習慣
撮影後は、全部を見返すのではなく「お気に入りの3枚」を選んでみてください。
その3枚に共通するものは何でしょうか?
構図?光?感情?——そこには、無意識に惹かれた“自分らしさ”が写っているはずです。
たった3枚でも、積み重ねれば立派なポートフォリオになります。
それが、後々“自分らしい写真”を言葉にできる力にもつながります。
“なぜこれを撮ったのか”を言葉にしてみる
一枚の写真について、「どうしてこれを撮ったんだろう」と考えてみてください。
そこに言葉を添えると、ただの記録写真が“物語”を持ちはじめます。
「夕焼けの中に、一人で歩く後ろ姿が寂しくて美しかった」
「母の笑顔を、ふと“未来の記憶”として残したくなった」
写真と言葉を組み合わせることで、あなたの写真はより深く、より温かく、誰かの心に届いていきます。
まとめ|“好き”から始まった写真は、ちゃんと育っていく
一眼レフカメラ初心者のあなたへ——設定も、構図も、すべてを完璧にする必要はありません。
大切なのは、“撮ってみたい”と思ったその気持ちに素直でいること。
迷ったら、シャッターを。
立ち止まったら、光を見上げて。
撮った写真の中に、今のあなたの心が息づいていることに、どうか気づいてください。
「撮ることが好きでよかった」と思える日が、きっと何度もやってきます。
その一枚一枚が、あなた自身の物語になっていくのですから。

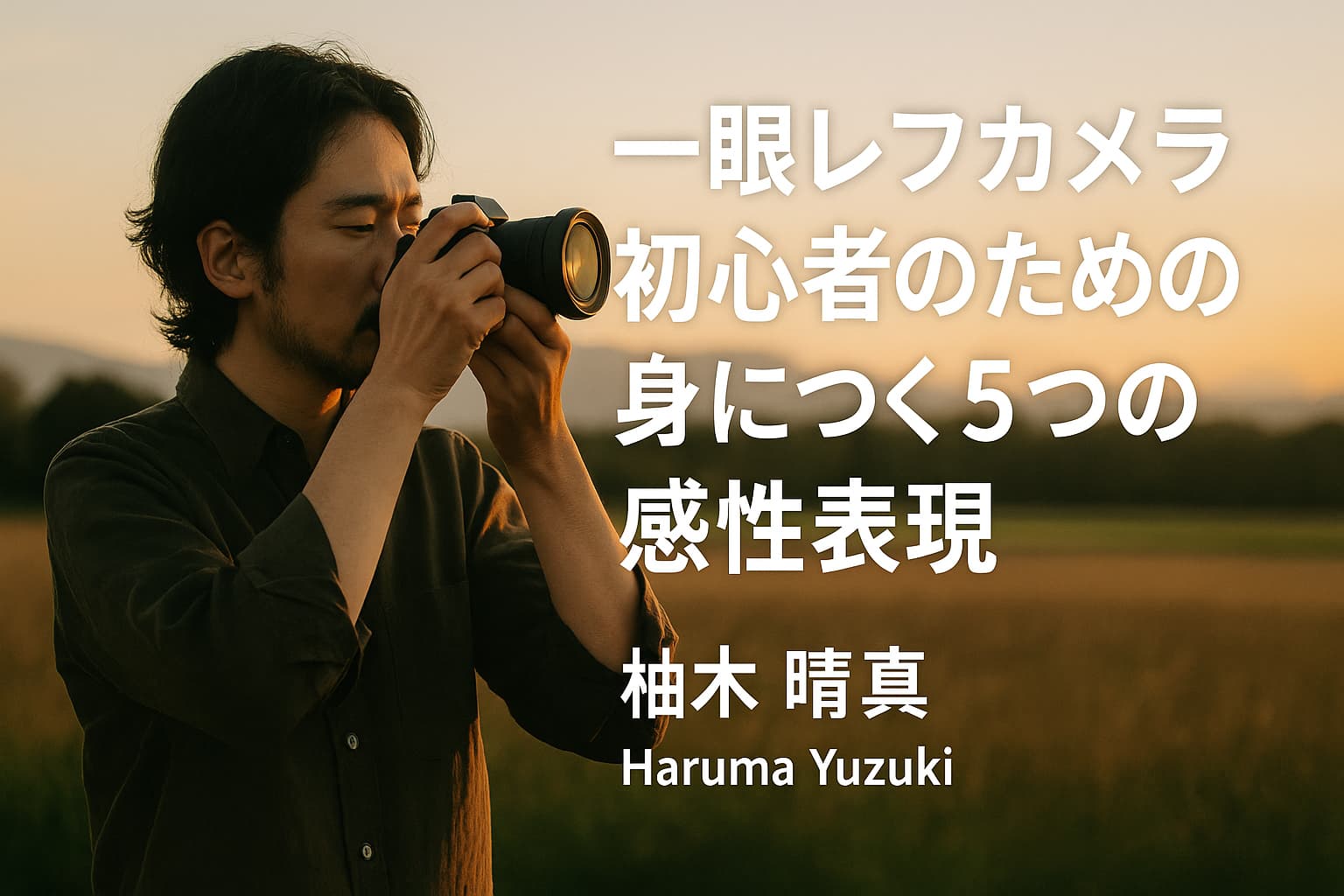


コメント