「また写真?」「SNSに上げたいだけでしょ?」──
そんな言葉に、ふと胸が詰まったことはありませんか。
趣味としてカメラを楽しんでいるだけなのに、なぜか“うざい”と思われてしまう。
そんな理不尽な空気に、言葉も出ないままシャッターを切れなくなったことが、私にもありました。
この記事では、“写真 趣味 うざい”というキーワードに込められた葛藤や痛みをひとつひとつ解きほぐしながら、写真を好きでいることを、もう一度肯定できるような言葉を綴っていきます。
「写真が趣味って、うざいの?」と言われてしまう瞬間
写真を趣味にしている人なら、一度は聞いたことがあるかもしれません。
「また写真撮ってるの?」「それ、自己満でしょ?」「SNSに載せたいだけじゃないの?」──
そんな言葉の数々は、言った本人に悪気がなかったとしても、聞く側にとっては十分すぎるほど鋭く刺さります。
それは、たとえば描いた絵を「暇つぶしでしょ」と言われるようなもの。音楽に夢中な人へ「うるさいな」と呟くようなもの。
写真が好きな気持ちは、誰かを困らせるためのものではないのに、なぜか「うざい」と思われてしまうことがあるのです。
ここでは、そんな誤解や偏見が生まれる場面や、その背後にある心理を丁寧に見つめていきます。
よくある「うざい」と思われる場面
たとえば、旅行やカフェでシャッターを切っているとき。
誰かがふとした表情を見せた瞬間にレンズを向けたとき。
「せっかくの時間なんだから、写真ばかり撮らないで」と言われることがあります。
もちろん、その場を楽しむことは大切。でも、私たちは決して“記録”だけを目的にしているわけではないんですよね。
その空気の匂い、その場の光、流れていた音楽──それらをあとからもう一度“感じる”ために、写真を撮っているんです。
けれど、それをうまく説明できないと、「目立ちたい」「承認欲求」といった言葉で一括りにされてしまう。
だからこそ、「うざい」と言われる場面には、コミュニケーションのすれ違いが潜んでいるのだと思います。
実際に言われて傷ついたエピソード
あるとき、私は友人と山へハイキングに行きました。
夕暮れ時、山の上から見えた逆光の景色があまりにも美しく、夢中でシャッターを切っていたんです。
すると背後から、「どうせインスタ用でしょ」と呟かれました。
その場では笑ってごまかしましたが、帰りの電車で、心の奥がじわじわと冷えていくのを感じました。
誰にも迷惑をかけたくなかった。ただ、その瞬間に感動して、残したかっただけだったのに。
言葉は記憶に残り、いつの間にか「またうざいって思われるかも」と自分にブレーキをかけるようになってしまったのです。
写真が好きという気持ちに、自分で影を差してしまった──それがいちばん、悲しかった。
なぜ写真趣味だけが批判されやすいのか
音楽や絵画、手芸やスポーツ──さまざまな趣味がある中で、なぜか写真は「うざい」と言われやすい。
それはおそらく、「他人に見せること」が前提になっているように見えてしまうから。
SNSとの親和性が高く、自己表現と結びつきやすいからこそ、批判や偏見の的にもなりやすいのです。
でも考えてみれば、どんな趣味にも“誰かに共有したくなる気持ち”はあるはず。
写真だけが特別“目立ちたがり”というわけではないのに、映像としてのインパクトが強いために誤解されやすいんですね。
私たちができるのは、「見せるために撮ってるんじゃない」という姿勢を、言葉でなく“写真そのもの”で静かに伝えていくことなのかもしれません。
傷ついた心にそっとピントを合わせる
誰かの何気ないひと言に心が傷ついたとき、レンズを構える手がふと止まることがあります。
「またうざいと思われたらどうしよう」──そんな思いが頭をよぎると、カメラが遠く感じてしまうことさえある。
でも、そんなときこそ一度深呼吸して、自分の“感受性”にそっとピントを合わせてみてほしいのです。
写真を撮ることは、本来とても個人的な行為。自分の心を、丁寧に見つめ直す時間でもあります。
この章では、「撮る気持ち」を取り戻すための視点を、少しだけ立ち止まりながら一緒に考えていきます。
誰かの目ではなく、自分の目で見ているか
「撮る」という行為は、本来自分の内側にある感情や関心をカタチにするものです。
でも、SNSが日常に溶け込んだ今、気づかないうちに“誰かにどう見えるか”を優先してしまうことがあります。
「いいねがつきそうか」「褒められる構図か」──そんな考えが先に立つと、本当に撮りたかったものがぼやけてしまう。
だからこそ、ときどき自分に問いかけてみてください。
「これは、誰のために撮りたいのか?」と。
他人の評価がなくても撮りたいと思える風景。それが、あなたにとって本当に大切な“シャッターの理由”です。
「撮りたい気持ち」がくれた救い
私にも、一度カメラから離れた時期がありました。
他人の目が気になって、何を撮っても「これでいいのか」と不安になってしまったからです。
けれど、ある日、雨上がりの路地で足を止めたとき──ふと、光に濡れる葉っぱに心を奪われました。
気づけば、手にはカメラがありました。
「誰かに見せたい」じゃなく、「ただ、この光を残したい」──その気持ちだけでシャッターを押したその瞬間、
少しだけ、自分を取り戻せた気がしたんです。
撮りたいという衝動は、ときに迷いや傷ついた心を静かに癒してくれる。写真は、そんな優しさを秘めた趣味なのだと思います。
言葉にならない感情を写すということ
写真には、言葉でうまく言えない気持ちを写す力があります。
「きれい」「懐かしい」「なぜか涙が出そう」──そんな感情を、ただの“像”の中に封じ込めることができる。
言葉にするには未完成すぎる感情も、光と影でなら表現できる。
だから私は、撮れなくなったときこそ写真に助けられてきました。
泣きたい気持ち、怒り、孤独、希望──それらは、誰かに説明しなくても、写真というかたちで確かに“残せる”んです。
「撮ること」は、気持ちを吐き出すための“もうひとつの言語”。
自分自身を守るために、レンズ越しに心を映していいのだと、私は思います。
それでも、写真が好きだと思える理由
「うざい」と言われても、それでもやっぱりカメラを持ちたくなる。
それはきっと、写真が「評価されるためのもの」じゃなく、「自分を取り戻す場所」だから。
他人の目が気になっても、周りがどう思っても、シャッターの向こうには、いつだって“自分だけの世界”が広がっています。
この章では、他人の声に惑わされそうになったとき、それでも写真が好きだと感じられる理由を、3つの視点から紐解いていきます。
自己表現と、自己肯定のあいだ
写真を撮ることは、単なる“記録”ではなく、じつはとても繊細な「自己表現」です。
でも、自己表現が評価されないとき──「うざい」と言われたとき──自己否定に陥りやすい。
そんなふうに感じたことはありませんか?
私たちが目にする世界は、他の誰とも同じじゃない。
その唯一無二の視点を形にすることで、私たちは「自分にも価値がある」と静かに確認しているのだと思います。
だからこそ、写真は“自己肯定”のための装置であり、心を守る“レンズ”でもあるのです。
写真は“誰かのため”じゃなくていい
SNSでの反応や、周囲からの言葉がどうしても気になる──それは自然なことです。
でも、その気持ちに縛られて苦しくなるくらいなら、「誰のために撮るか」をもう一度見つめ直してみましょう。
誰かの“いいね”のためじゃなく、自分の“いいな”のためにシャッターを切っていた頃。
季節の匂いや、光のにじみ、誰かの仕草に心が動いて、夢中で撮っていた日々。
あの気持ちを思い出せたなら、もう「うざい」なんて言葉は届かない。
写真は、まず自分自身に優しくするための行為なんです。
「うざい」と言う声を、静かに超えていく
世の中には、どんな趣味にも“好き勝手に言う人”がいます。
でも、写真はそれを「写す」ことで、そっと乗り越えることができる。
たとえば、何も言い返さなくても、誰かのふとした笑顔を写した一枚が、その人を笑顔にさせるかもしれない。
あるいは、黙って夕陽を撮ったその写真が、誰かの心を照らすかもしれない。
言葉にしなくても、「うざい」という声を超えて、何かを伝えることができる──
それが、写真という表現の持つ“静かな力”だと思います。
好きなものを、好きなままでいていい
「うざい」と言われたとき、それがどんなにさりげない言葉でも、心には確かに跡が残ります。
趣味であるはずの写真が、急に重たく感じられて、シャッターを切るのが怖くなる。
だけど──それでも私たちは、写真が好きでいていい。
誰かに評価されなくても、誰かに笑われたとしても、あなたの「撮りたい気持ち」は、何ものにも汚されないのだから。
写真という趣味は、ただの趣味じゃない。
それは、自分自身を大切にすることと、とてもよく似ています。
光に惹かれる気持ち、残したいと思う瞬間、胸がきゅっとなるあの一秒──すべてが“生きている証拠”です。
他人の声よりも、あなたの心の声を信じてください。
カメラを構えたあなたの目線は、世界に小さな優しさを見つけようとしている。
たとえ「うざい」と言われたとしても、その優しさを止める必要なんて、どこにもないんです。
だから今日も、好きなものを、好きなままで。
シャッターを押すたびに、あなたの中の“ほんとう”が、少しずつ育っていきますように。

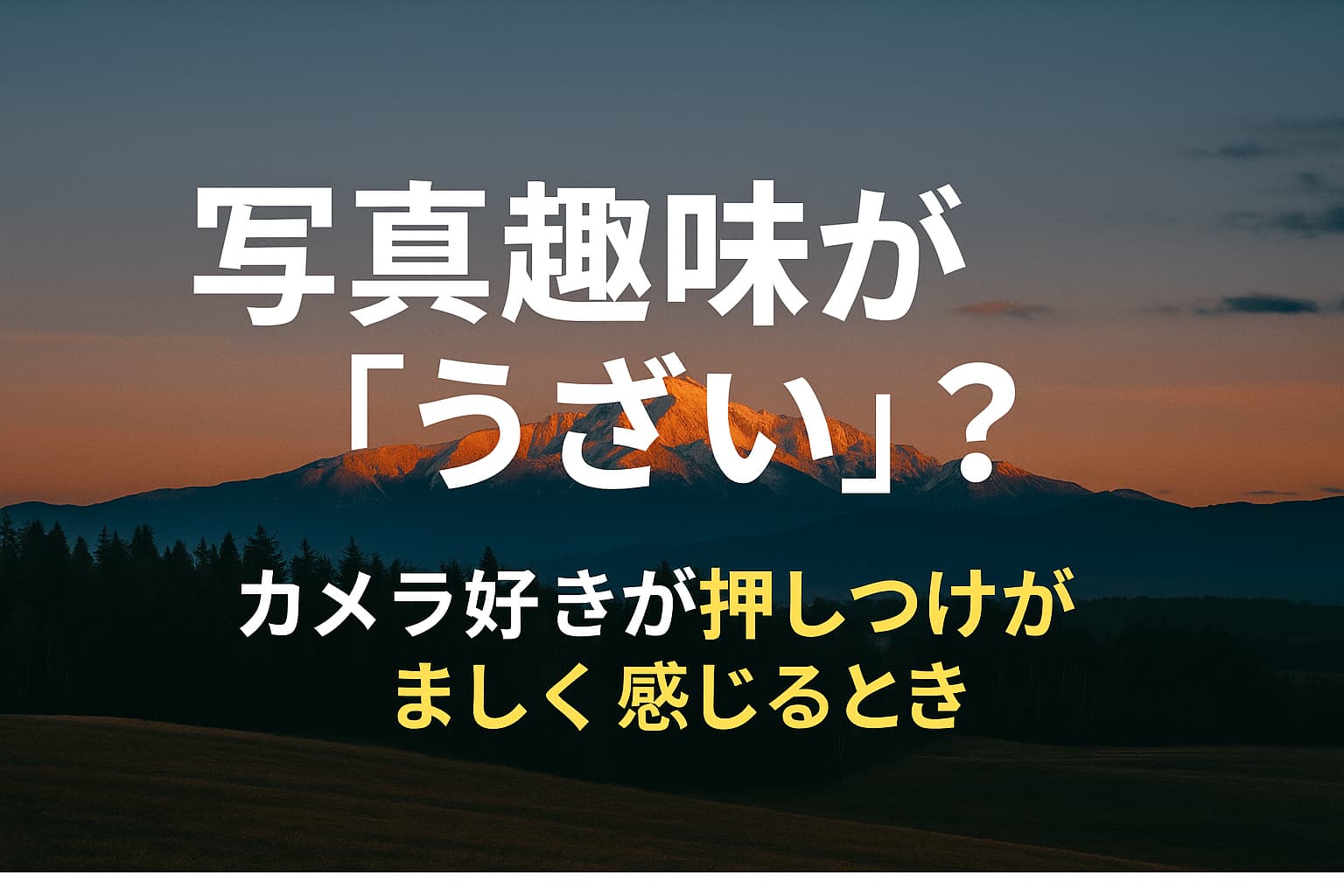
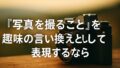

コメント